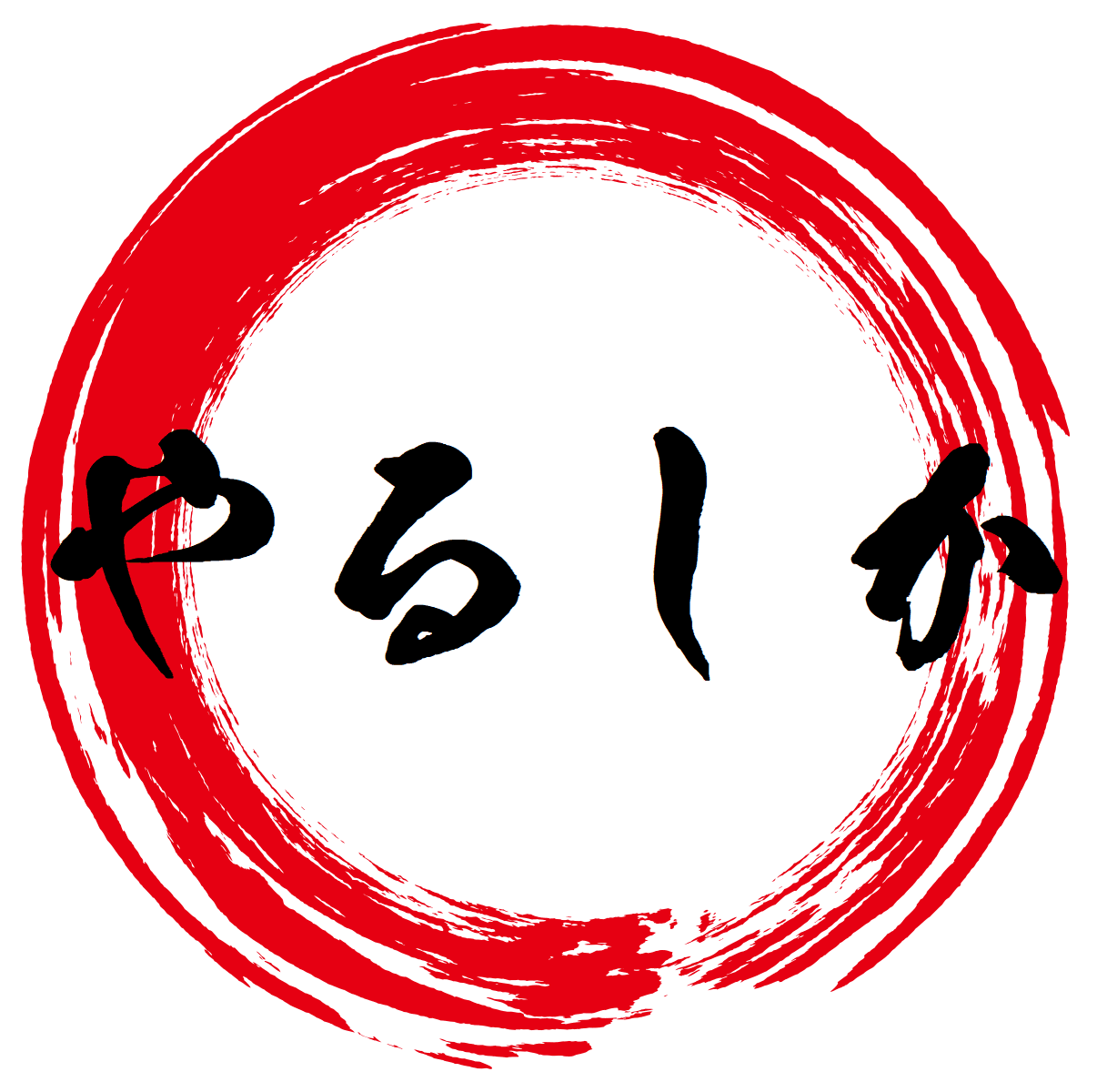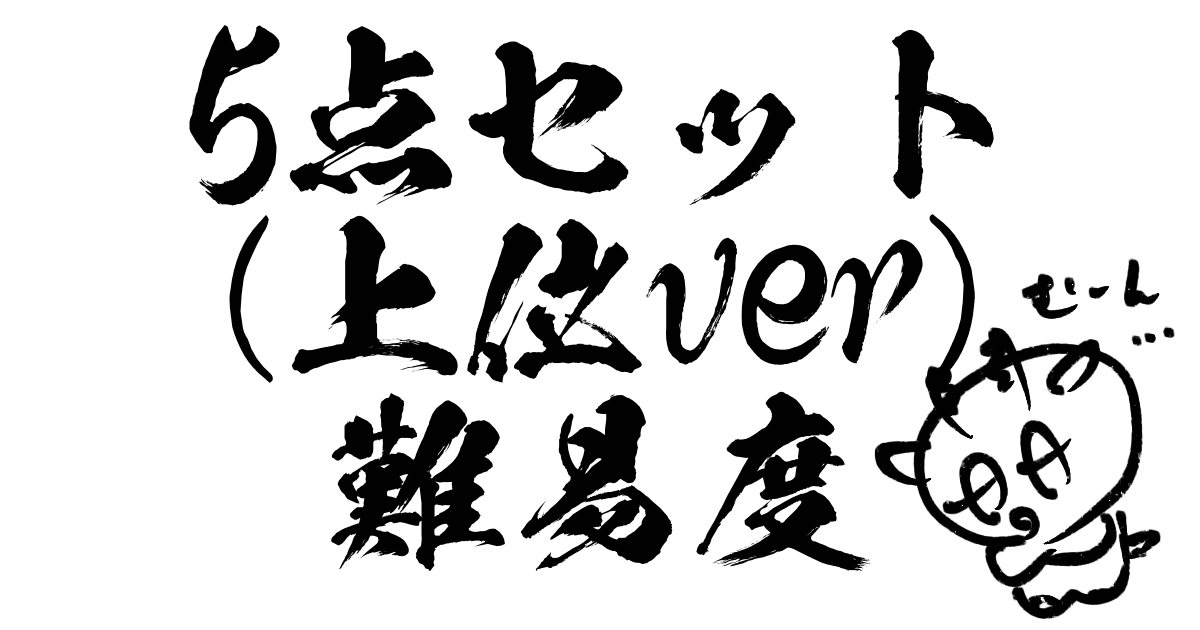ビルメン5点セットとは
ビルメン5点セット
- 第二種電気工事士
- 危険物取扱者乙種4類
- 二級ボイラー
- 第三種冷凍機械責任者
- 消防設備士(主には1類、4類、乙種6類)
のことですが、

ビルメン5点セット上位バージョンとは
主には
ビルメン5点セット上位バージョン
- 第一種電気工事士
- 危険物取扱者甲種取扱者
- 一級ボイラー
- 第一種冷凍機械責任者
- 消防設備士(甲種特類込みで全類)
のことです。
てか自分が勝手に作りました(笑)
第一種電気工事士は資格取得ちゃうやん!(第一種は試験合格をしたとしても、実務経験が3年ないと資格としては取得したことにならない)
ボイラーも特級どころか、一級も資格取得ちゃうやん!(こちらも試験合格までで、一級をとるには二級取得後にボイラーの取り扱い業務を2年以上、もしくはボイラー取扱作業主任者の経験が1年以上必要)
なんてツッコミはここでは無しでお願いします(笑)
あくまで実務経験なくても試験合格で取れる範囲でという事で(笑)
当然なんですが、試験によって難易度は異なります。
ここでは自分が感じた、体感した感じの試験の難易度を書いてみます。
もちろんですが、試験運や個人差などもあるので、あくまでも参考程度にとどめておいてください。

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
ビルメン5点セットの難易度
難易度は一般的に言われいる難易度と、自分が体感した難易度は違うことはあると思います。
これは試験運というものが関係しているからですね。
なぜこういうことが起こるのかというと、問題も人間が作っているものなので、
難易度をいつも同じにすることはできません。
なので、同じ試験でもやたら難しい回や簡単な回があったりするわけです。
おそらく一般的に言われているであろう難易度は
ビルメン4点セットの難易度
- 第三種冷凍機械責任者>第二種電気工事士>二級ボイラー技士>危険物取扱者乙種4類
だと思います。
これに5点セット5点目の消防設備士の1類、4類、乙種6類が加わると
ビルメン5点セットの難易度
- 第三種冷凍機械責任者≧消防設備士甲種1類>第二種電気工事士≧消防設備士乙種6類>二級ボイラー技士>危険物取扱者乙種4類
くらいのイメージですかね。
もう主観が入ってる気がします(笑)
そう、たったこれだけでも難易度の優劣をつけるのは難しいんです。
なのであくまで経験や体感した個人的難易度になるとは思いますが、よろしくお願いします。
全体の個人的難易度
僕が受けた試験全体の印象的には
でした。
正味試験運もかかわってくるのであくまで参考程度にとどめておいてください。
難易度というか、試験受けたのときの絶望感順です(笑)
不思議と点数と難易度って比例しないんですよね。
正味な難易度はどうなんでしょうね。
試験運っていうものがある以上測りづらいですし、それでも全く変わってきますね。
この中で落ちたのは、一級ボイラーと消防設備士甲種5類なんですが、
2回目は割に簡単でした。これが一回目にきてたらいけてたので、本当運の要素は結構あります。
二級ボイラーが?
二級ボイラーがこの位置に来るのは意外だと思いますし、エアプだと思われても仕方がないのですが、
本当に落ちたかと思っていました。
なので皆さんも二級ボイラーに落ちたとしても、なにも恥ずべきことはないです!
落ちてしまってもきっと難しい回に当たってしまったのでしょう。
受験料も高い方だし、試験会場に行くのも結構時間かかったりするので、大変ですよね。悔しいですよね。
これは他の試験でも全然言えることですね。
消防設備士甲種2類は電気の科目がめんどくさかったですし、難しすぎて落ちたと思ってましたが、
試験後思い返す範囲で自己採点すると、間違えて申請してしまった電気科目に救われていて、
いけるかもという感情にうっすら変わっていきました。
一級ボイラーは落ちてるけど、二級ボイラーの方が難しかったと思います(笑)
ほんと相性が悪かったですね。
危険物甲種特類はベタに物理・化学が難点でしたね。
受ける前は不安でしょうがなかったですが、公論様様です。
冷凍機械(保安)は試験本番で最初にざっと通してできたと思ったのは3~4割程度で、
一番絶望感を感じていました。
15問中13問正解だったのはびっくりしました。
絵によって救われた感がえげつなかったです。
絵によって、ほぼ消去法で答えを導き出した感じです。
冷凍機械(学識)は四則演算ができたら特に大したことはないのですが、式が長くなってしまうのでめんどくさかったです。
講習オンライン一期生ということもあり、性分的に全てやらないと不安でした。
予想を立て、ある程度取捨選択できるともっと楽に行けると思います。
電気工事士の実技は除外
電気工事士の実技は外しています。
難易度っていうかこれは試験としては別物なので、
暗記物としては大したことはないです。
ただどの試験よりもずば抜けて緊張はしました。
そういった意味ではこの中に入れるとすると、割に上位には来るのかなとは思います。
勉強してる段階の難易度
ちなみに勉強してる感じの段階だとまた変わってきて、
といった感じですね。
僕は文系で、やっぱり物理化学はよくわかんないし弱いです。
勉強中はボイラーは割に簡単に思いました。
取得する順番
入り組みすぎて厳密に組むことは中々難しかったです。
ビルメン5点セット上位バージョンを取る順番についてなのですが、
各資格ごとの順番になってしまいますが、
急ぎではない人は(大体の人は5点の基本的なもの以外で急ぐ必要もないとは思いますが)
ビルメン5点セット上位バージョンを取る順番
- 第二種電気工事士→第一種電気工事士 ※試験日のベースにする
- 危険物乙4→乙3、5、6→甲種
- 二級ボイラー→一級ボイラー
- 消防設備士6→5→1→2→3→4→7→特
- 第一種冷凍機械責任者を講習で取る(第三種や二種を挟んでもいいと思います) ※試験日のベースにする
て感じですかね。
これら全てを織り交ぜた順番はさすがに入り組みすぎて、書けません(笑)
地域によるものもありますし、(消防設備士でも簡単に複数受けられない地域の方もいるとは思います)
個人の休日や試験日があまりにバラバラなので、
受けれそうな日のスケジュールを組んで取っていってください。
僕は特に深く考えず、受けれそうな日から受けていましたね。
つまりそういうことです。
わたしのプロフィールからもわかる通り、順番は特に気にしなくても取れます。
ただ、試験日のスケジュールを組むベースはあります。
受験機会が少ないものから組んでいくのがセオリーになると思います。
なので電気工事士、冷凍機械責任者あたりをベースにしましょう。
その間に危険物、ボイラー技士、消防津設備士などを入れんでいくイメージです。
とはいっても、消防設備士は電気工事士の免状を取得した後の方が、甲種の受験資格にもなりますし、
電気工事士の免除を使って取得していった方が圧倒的に早く有利になります。
なので最初のうちで甲種の取得を視野に入れたい人は乙種6類と乙種7類くらいしか取得できませんね。
乙種を狙う方でしたら問題なく受験できます。
けれども甲種は乙種に毛が生えた程度なので、ついでに勉強しても難易度は大して変わらないんじゃないかなと思っています。
乙種7類は甲種のどれかと同時受験した方が効率的だと思うので、電気工事士は早い内に取るのが正解のような気はします。
早く取りたい人は、近隣の県の受験も積極的に取り入れていきましょう。
冷凍機械責任者の場合
講習なら、いきなり一種を目指しても全然いいと思います。
三種も一種も意味わからないので、僕にとっては大した差はないというか、三種はやってません。
エンタルピーの意味も分かってません。
冷凍機械責任者は他の試験と相関は少なくとも僕は感じませんでした。
ほんとは何かと相関はあるのかもしれないですけど(ボイラーとか?)、意識できないほどだったので、そんな感じでもいけます。
危険物取扱者の場合
危険物取扱者は乙種は誰でも受けることができます。
ただし甲種は、
の乙種が4つ以上合格した場合にのみ受験資格が与えられます。
厳密には理系の化学系の大学の単位があるとか、他にも受験資格はあるみたいですが、
一般的には乙種を4つ狙うことになるでしょう。
危険物も4類その他の類を計4つ合格してから甲種を狙うなら、
甲種では1~6類までの性質・消化の知識が広く浅く必要ですので、乙種4つ合格後に早めに取れるなら取ったほうがいいですね。
危険物乙4と二級ボイラーは少し相関あった感じしますが、
そこまで相関してないのであまり気にしなくていいレベルです。
けれども少しは相関しているので、狙えるなら近い内に受けていてもいいと思いますね。
変則的な取り方として、
一般的には乙4から取って、ほかを狙うと思うのですが、
上記の通り
から4つなので、
乙4を取らずに、
例えば2、3、5、6類でも狙う事は可能です。
甲種を取れば乙4分も扱えるので問題はないですが、
免状を見られたときにどういう空気になるかは気になるところではあります。
ボイラー技士の場合
ボイラー試験は、二級に合格して免状が発行された後じゃないと、一級は受けられないようになっています。
二級の免状を取得する際、試験合格だけではだめで、実技講習という3日間の講習を受ける必要があるのですが、
そのボイラーの講習を受けた後のほうが試験勉強が理解しやすいのは経験上そうかもしれません。(最初はあんま関係ないだろうと思ってましたが講習を受けて理解が進んだ)
ただ勉強を始めた後で講習を受けても全く問題はないです。
僕自身がそうだったのですが、
最初にある程度過去問などで勉強しておいて、講習を受けてからまた勉強するサンドイッチが最強ではありますね。
実際講習で手を動かしてやることもあるので、あぁ、こういうことだったのかと理解が進むことがありました。
電気工事士の場合
これ、意外にどこにも書かれてなくて当時結構悩んだので書きます。
電気工事士はいきなり第一種から受けることは可能です。
そこで僕が思ったのが、第一種の試験に合格すれば、第二種の免状は発行してもらえるの?
でした。
結論として、申請もできないし、発行されません。
当時はお金もかかるし、上位の第一種をいきなり受けて、二種は面倒だし受けたくないなって思ったものです。
なのでもしそう考えてた人がいたら、あきらめて二種を受けましょう。
ちなみに一種を受けて合格してから二種を受けることも全然できます。
一種は受かっても二種が落ちることなんてのもあり得るわけです。
なんか変な感じですね。
あとは、第一種の試験に受かって、実務経験も3年あって、第一種の免状が発行してもらえるなら
二種を持ってなくてもいいんですよ。
けれども大体の人はそうじゃありませんので、
第二種を受けて免状を発行する必要があるって事ですね。
消防設備士の場合
消防設備士難易度
まずは消防設備士全体の難易度についてです。
一般的に言われている難易度は
甲1>甲3>甲2>特類>甲4>甲5>乙6>乙7
くらいなんですかね。
個人的難易度では
甲2>甲1>甲3>甲5≧乙6>特類>甲4>乙7
でした。
唯一落ちた甲5は落ちといてなんですが、めちゃめちゃむずいかって言ったら特にそうでもないんですよね。
乙6は以外に難しかったですね。
甲4がここの位置にあるのは不思議かもしれませんが、公論本をやっていれば比較的簡単なのでこんなもんです。
消防設備士の甲種を受ける予定でしたら
文系でしたら第二種電気工事士の資格は必須です。
第二種電気工事士は受験資格もなく誰でも挑戦できる資格です。
ちなみに電気工事士は他の試験の内容とはあまり相関ないっちゃないんですが、
もし消防設備士で電気基礎という科目の免除をしない場合は、電気の計算が役に立つかもしれません。
僕は受験の申請をミスって消防設備士の電気基礎を免除しなかったことがありますが…。
第二種電気工事士を取得した後は
どれからでもいいです。
好きな順番でとりましょう。
僕は特にこだわりはなかったですが、早く終わらせたかったので
スケジュールの中で行けそうな日と場所を優先的に選んでいきました。
とまぁそれではあまりにも不親切なので、一応相関がありそうなものを挙げていきます。
消防設備士の1類と2類は両方とも狙うなら近いうちに取ったほうがいいと思います。
私は1類と2類を受験した期間がまあまあ離れてたので、1類の半年後に受けた2類はほぼゼロからの感覚でした。
これは近い内に取っておけばよかったなーと思いました。
3類は1、2類とよく並べられるのですが,そこまで相関なかったですね。
機械基礎を免除したかったら1~3類のどれかを取っておいてもいいですが、
結局5類や6類で機械基礎はやらなければいけないんですよね。
厳密には5類を取った後だと6類の機械基礎は免除できるんですが、あまりないようなケースのような気がします。
考えようによりますが、機械基礎はのちに得点源になる可能性は秘めています。
僕は機械基礎は大嫌いでした。
だけど、免除せずにいたんですが、最終的には得点源になった感じでした。
6類は案外、危険物や消防設備とまあまあ相関してるなーってところもありました。きっちり覚えてて損はないです。
4類と7類は電気基礎が共通しているので、少し関係ある気もしますが、ほとんどの人が免除すると思うので無視していいレベルです。
もし早めに全て制覇したいのならおすすめは
6→5→1→2→3→4→(7)→特(7類は同時受験でも、一番最初でも好きなところに入れて下さい)
この順番の理由は強制的に受けさせられる機械基礎を早めにとっちめたいからですね。
これらをやっていく上で機械基礎に慣れてきたと思ったら、2類と3類も機械基礎を受けて得点源にしたらいいと思います。
1類と2類は近い内に受験した方がいいというのもあります。
6類と5類は乙種と甲種の場合は同時受験でいける場合もあるかもしれません。
よっぽど機械基礎が嫌いなら、5類を受けて、受かってから6類を機械基礎の免除ありで申請してもいいかもしれないですね。
上記はあくまで全て狙う人の順番であり、需要は無視しています。
需要重視かつ全て制覇するつもりの人は
6→4→1→2→3→5→(7)→特
の順番でいいと思います。
もっと言えば最初の方の
6→4→1
だけでも十分ではないかと思います。
全部取ろうと思っている人は、需要順とか考える必要はあまりないんじゃないかとは思いますが、
僕もなんか最初は需要順の方がいいのかなーなんて思ってましたが(甲1&乙6同時受験)、
途中から割にどうでもよくなってしまいました。
途中で面倒くさくなって、全部の取得をやめたくなる可能性も考慮したら、需要順でもいいのかもしれないですね。
逆に言えばそれ(6→4→1)をしてしまうからもういいかーってなる可能性もあります(笑)
もし短期間で取りたいやいって思った場合
注意しなければならないことがあります。
僕は特類を一番最後に受けたのですが、途中でミスりました。
特類の受験資格は甲種1、2、3類のうちのどれか一つ
甲種4類と甲種5類の両方
の計3つが必要になります。
あまり深く考えず取っていったので、甲種特類を受けるための受験資格が、願書に3日、間に合いませんでした。
ほぼ同時に受けた甲種5類と甲種4類(次の日受験)でしたが、甲種4類の免状発行がやたら遅かったんですよね。
本当に地域差があるので、そこまで想定していない自分が悪かったのですが、
何とか、合格証明書をコピーして送って、
免状来たらすぐ出しますから受けさせてほしいです。って書いてもダメでしたね。←迷惑なのでやめましょう
そのおかげで本来3月に受けて9か月で消防設備士は終わらせたかったんですが、6月まで受けられなくて足踏みしてしまいました。
3か月とはいえ、知識も抜けていきますし、その間第一種冷凍機械の講習試験もあったので、これはだいぶやってしましました。
受けれないおかげで、その勉強するはずだった空いた期間が暇だったんですが(結構さぼっちゃいました)、そのツケは後で忙しさとしてしっかり回ってきました。
といった感じで感覚と経験でまとめてみました。
受ける数が多いと、なかなか冒頭に挙げた順番通りにはいかないと思います。
参考程度に留めておいてください。