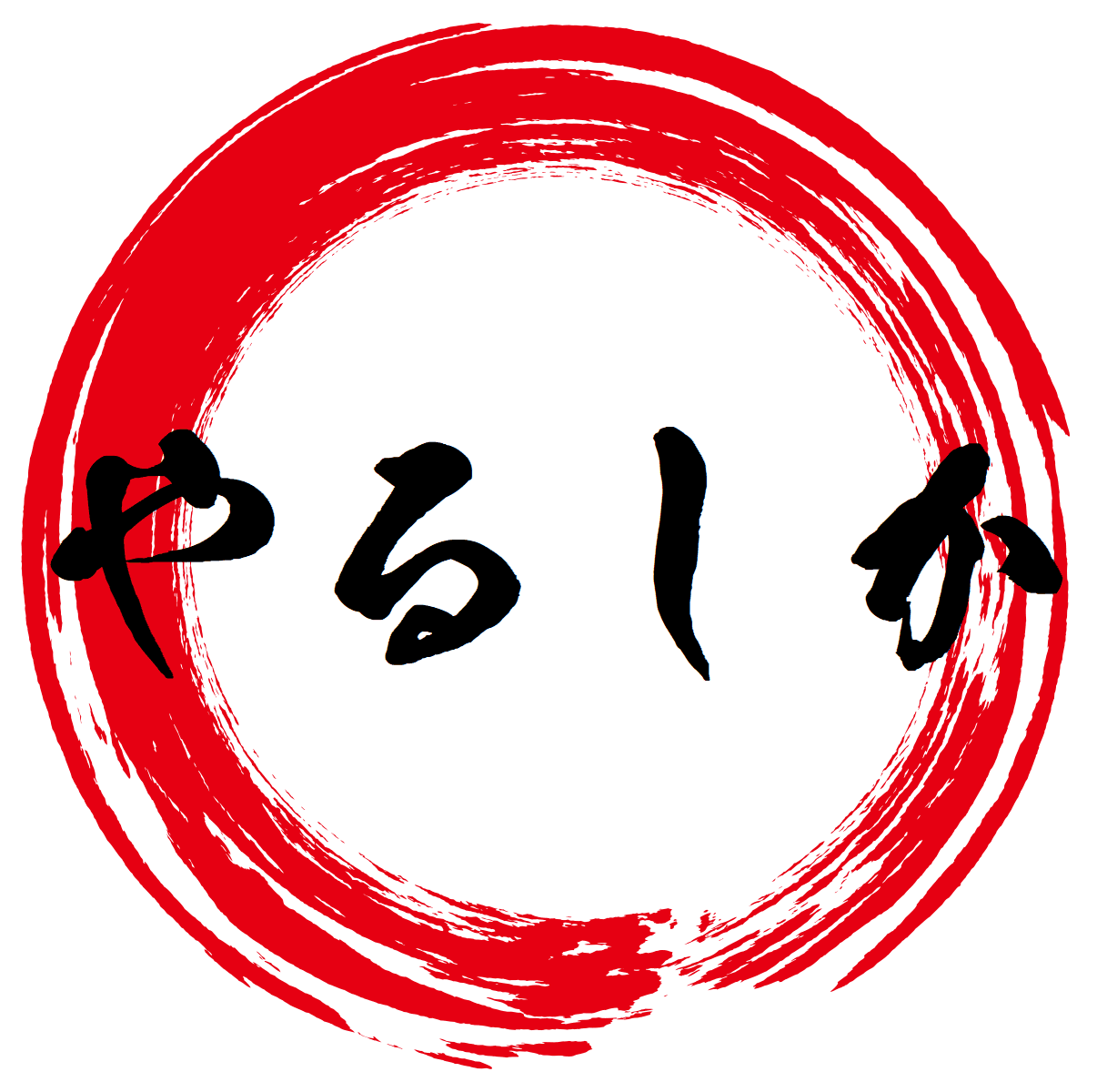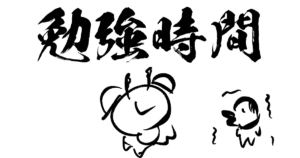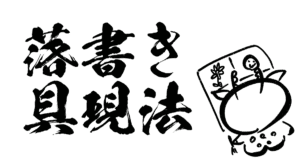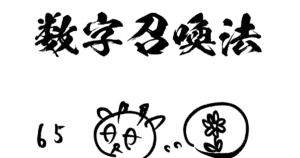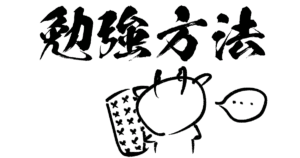消防設備士 特類(甲種特類)は他の甲種とは毛色が違います。
受験資格も少し特殊でわかりにくいです。
消防設備士 特類の受験資格
- 甲種1類、甲種2類、甲種3類のいずれか1つ
- 甲種4類
- 甲種5類
この「合計3種類以上の甲種免状(4類+5類+1~3類のいずれか)」
を所持していることが、甲種特類の受験資格となっています。
注意点はその時点で交付がされてて手元に免状があることです。
交付が遅い県と早い県があり僕はそれを見誤っていたので、
7ヶ月ぐらいで全類合格する予定が、大幅に遅れ1年になってしまいました。
3日だけ交付が遅れたので、相当悔しかったのを覚えています。
3日なのでダメもとで交渉しましたが当然ダメでした。
全てマークシート方式なので、実技はないです。
そもそも消防設備士 特類って何という方はこちら。(準備中)
消防設備士 特類「試験概要」について知りたい方はこちら。(準備中)

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
消防設備士 特類の勉強時間
びっくりするくらい特類の勉強時間に対する情報がないので私がネットで唯一の情報源なのですが、
勉強時間を測ったことがないので、フルタイムで働いて試験までの20日間って感じですね。
フルタイムで仕事したり、残業もちょこちょこあるので、明確には言えないのですが、帰っている間の時間です。
本当は知識が残っているうちに早めに受けたかったんですが、数日だけ免状が届くのが間に合わず、想定してた4か月後に受ける羽目になってしまいました。(仕方ないので第一種冷凍機械責任者の講習試験に集中し、その20日後に甲種特類を受験)
他に書かれている勉強時間は消防設備士甲種でくくられています。
しかし全く性質が違うので、特類を他の甲種と一緒にくくってはいけないかなーと思いますね。
バックボーン(経験者や理系など)や試験運などの要素もあり、人それぞれなので、
例えば20日以上かかってしまうといっても全く気にすることはないです。
正直僕は勉強時間というのは目安にはすることはあるけど、自分で測ったり、これくらい必要だと決めるのはあまり好きではないんです。
なので時間は測ってないです。
大体これくらいやったかなーくらいの感覚でOKで、
勉強時間を目標にしてしまうと、その時間が迫ってきた時に思ったより覚えていなかったりしたら、焦ったり劣等感を感じてしまいかねないですから。
なので、僕は勉強時間は計らないで自分のできる限りのことをやるというのを推奨します。
実際やってみると本当にただの参考値だなって思います。
あまりに無謀なことをやってもしょうがないので、一応参考にはしますけどね。
その期間でいけるかいけないかの目安です。
なのでここを見て期間内でいけそうかなーとざっくりした判断に使ってください。
勉強時間についての僕の考え方は以下になります。
消防設備士 特類に過去問はあるか?
消防設備士 特類に過去問はないとされております。
というのも試験自体が問題用紙の持ち帰りも不可であり、ほんの一部を除いて公表されておりません。
とはいえ、消防試験センターから公表されているこの一部の過去問からも出ることは経験上普通にあったので、
ぜひ目を通しておくことをお勧めします。
次ではおすすめするテキストを紹介しております。
消防設備士 特類のおすすめテキスト
つ、つ、ついに待望の特類のテキストが出ました!
どれか一つ選ぶとすれば間違いなくこれでしょう。
それまでは正味以下のテキストしか選択肢がなかったです。
2013年発売ですから、実に12年ぶりの特類の新刊になります。
あとよく言われるものとしては以下の書籍ですね。
「はじめて学ぶ建物と火災」は特類の過去問ともテキストとも違うので、参考書として使う感じです。
ほかはそれまでに使ったテキストから勉強していきました。
消防設備士 特類の勉強方法
ラクラクわかる! 特類消防設備士 集中ゼミラクラクわかる! 特類消防設備士 集中ゼミ
をやりこみましょう。
あとは甲種1類~5類までの勉強ですね。
6類と7類からは出ないです。
各類の法令は勉強しなくてもいいですが、共通法令からは少し出るので公論出版の本で復習しておきましょう。
特類を見越している方は、これまでに使ったテキストやノートは絶対に捨てないでください。
あと絶対に勢いで取得してしまった方がいいです。
特類特有の勉強はまだいいのですが、1~5類までの復習の為に勉強しなおすのが効率悪すぎます。
ただでさえめちゃくちゃ忘れてました。
だからさっと取ってしまいたかったんですよね。
勉強方法(全試験共通)
他の試験にも共通する勉強方法についてはこちらをご覧ください。
ビルメン資格最短取得を実現させた記憶術(落書き具現法&数字召喚法)も紹介していますので、どうぞ。