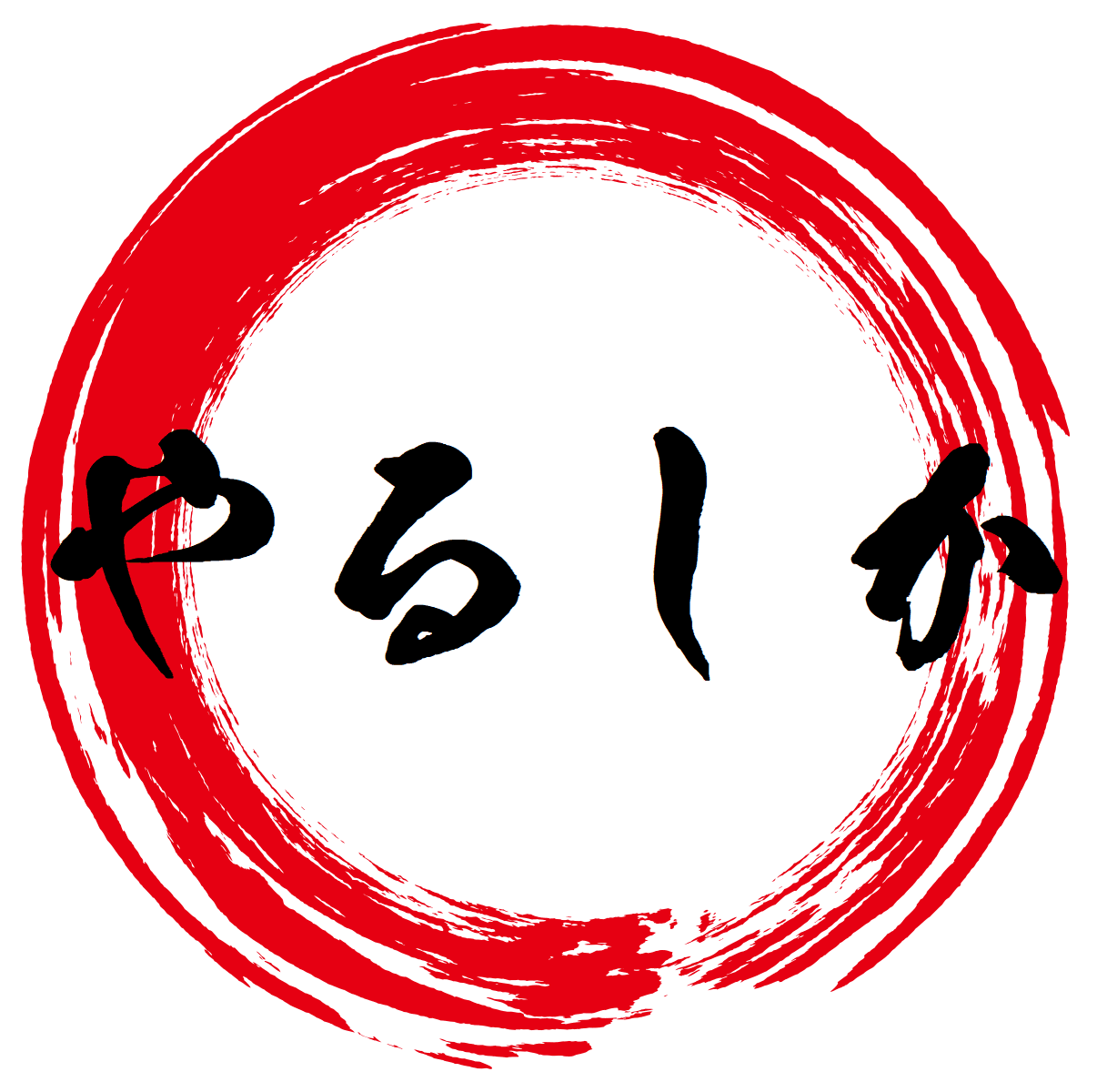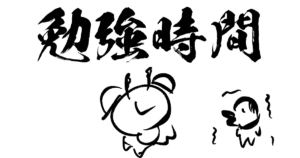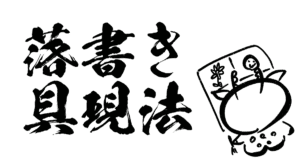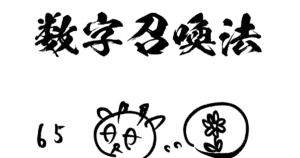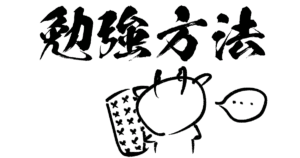この記事はコラムだと思ってあまり参考にしないでください(笑)
第三種電気主任技術者
通称電験、電験三種は僕の場合は12月の末から始めたので3カ月(全科目一発合格)くらいでした。
「電験三種がかるた大会になっちゃった」
と聞いたので参加してみました(かるた大会の理由は後述します)。
というのも僕の勉強法と相性がめちゃくちゃよかったからです。
過去問に出てたのは100%取れましたね。
そもそも第三種電気主任技術者って何という方はこちら。(準備中)
第三種電気主任技術者「試験概要」について知りたい方はこちら。(準備中)

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
電験三種の勉強時間
いろんなところを見た結果、大体以下の感じです。
第三種電気主任技術者の勉強時間の目安
- 最低でも1,000時間程度
- 400時間~600時間(理系)600時間~800時間(それ以外)
- 理論500時間 電力200時間 法規400時間 機械500時間
- 理論260時間 電力90時間 法規90時間 機械195時間
- 理論250時間 電力100〜200時間(電気工学系出身者)200〜300時間(文系出身者)
- 機械100〜200時間(電気工学系出身者)200〜300時間(文系出身者)法規50〜100時間
- 理論160時間(不合格)電力160時間(合格)機械160時間(合格)法規90時間(合格)
- 500時間~600時間(理系)800時間~1,000時間(文系、初学者)
- 340時間(電子系学科大卒)
- 700時間
- 2,190時間
- 5カ月
一般的によく言われるのはやはり1,000時間ではないでしょうか
一口に勉強時間と言ってもバックボーン( 理系など)や試験運などの要素もあり、人それぞれなので、
例えば1000時間以上かかってしまうといっても全く気にすることはないです。
というより、僕は勉強時間は計らないでやる事を推奨しますね。
大体これくらいやったかなーくらいの感覚で、勉強時間を目標にしてしまうと、
思ったより覚えていなかったりしたら焦ったり、劣等感を感じてしまいかねないですから、
自分のできる限りのことをやるというのを推奨します。
僕の場合勉強(?)期間は3カ月くらいです。
私は超ド文系(無系)で
3月23日の試験で、年末から始めました。
正直今回のは最も勉強とは言えない感じでした。
勉強時間についての僕の考え方は以下になります。
電験三種に過去問はあるか?
第三種電気主任技術者に過去問はあります。
過去問率が高く丸暗記できれば合格は可能です。
かるた大会ってのは
要は過去問から同じ問題と解答が出るから、計算できなくても解答を覚えていればできるよ
って揶揄や皮肉なんですね。
なーんか個人的にこういういう仕組みはあまりよくないような気はしてますが、ここではそれは置いておきます。
取得しても無茶苦茶虚しかったです。
次はおすすめテキストなんですが、過去問集=おすすめテキストですので、次で紹介します。
電験三種のおすすめテキスト
どう考えても近年の傾向に寄せに行った過去問集ですね(笑)
めちゃくちゃ需要が分かっています。
実は過去問は平成7年(1995年)以降から出題されます。
それ以前には試験も過去問も当然あるのですが、科目が変わっているというか
簡単に言えば節目が平成7年からになるので、ここから過去問を採用しているといった感じですね。
しかもこの過去問集は問題をかいつまんでいるわけではなく、しっかり全問載せています。
ただ、その辺の年度くらい前の過去問からの出題率は高いとは言えません。
けれども出るのは出るから過去問からの点数を稼ぐつもりなら、やっておいた方がいいといった感じです。
法規はやはり最新のものが必要というか、科目の性質上出版されない可能性はありますね。
そして法規は過去問率が高いということもあり、次のテキストで十分対応可能です。
過去問で合格を狙う場合、上記までは必須といった感じでしょうか。
めちゃくちゃ範囲は広いんですけどね。
上記は平成7年~平成19年分までしかないので、それ以上が欲しかったら下記のものになります。
※また明日貼ります
ただこれを買わなくても合格はできます。
電験王という電験三種の過去問をまとめてくれているサイトがあるので、こちらでもいいと思います。
ここがあったら十分な気がしますね。
電験三種の勉強方法
上記の第三種電気主任技術者の過去問をとにかく繰りかえしやりましょう。
ただ、結構過去問率は合格点かつかつなんですよ。
要は科目によっては合格点の60点分ギリギリしか過去問は出ません。
特に電力って科目はほんとにギリギリでした。
それが分かっていたので電力は文章問題が多いということもあり、ここは割にちゃんと令和ぐらいからの過去問の文章問題はやりました。
めちゃくちゃ紛らわしい問題がいくつもあって苦手でしたね。
あと、電気工事士と違うのは、全く同じ文言での問題は出ないことがある。
ということですね。
電気工事士はご丁寧にコピペさながらの問題だったので紐づけしやすく計算問題は逆に得点源でしたが、
電験三種で同じことをしようとしたらすこし難しいとは思います。
僕もまともにやってたんじゃ時間は足りないのでいろいろ工夫はしました。
CBT方式か筆記方式か
僕の場合、CBT(めっちゃBTCって間違える)は何回も行くのがめんどくさかったのでマークシート試験本番一日で終わらせました。
一日まるまる拘束もしんどいっちゃしんどいですけど効率はいいです。
2000問30年分を解答だけとはいえ一問も間違えずに覚えなきゃいけないので、
それなりに大変ですけど、過去問は100%覚えていきましたし、実際試験で出た過去問は正解率100%でした。
2000問?本当にそんなことが可能なのか?
僕の勉強法なら可能なんです。
この勉強法が暗記に超特化しているからです。
過去問以外のはあとは勉強した分か勘か適当かですが、(まぁそれなりに戦略は立てたんですけど)。
6割取れることは確信してたので、すべて受け終わって、精神的には余裕でしたね。
トータル、試験中は暇でした。
そこはスタイルなので、
例えばCBTで分散させるもよし、数年長期計画でとるもよし(6回もチャンスがあります)
今の試験の方式ならいつかは取れると思います。
勉強方法(全試験共通)
他の試験にも共通する勉強方法についてはこちらをご覧ください。
ビルメン資格最短取得を実現させた記憶術(落書き具現法&数字召喚法)も紹介していますので、どうぞ。