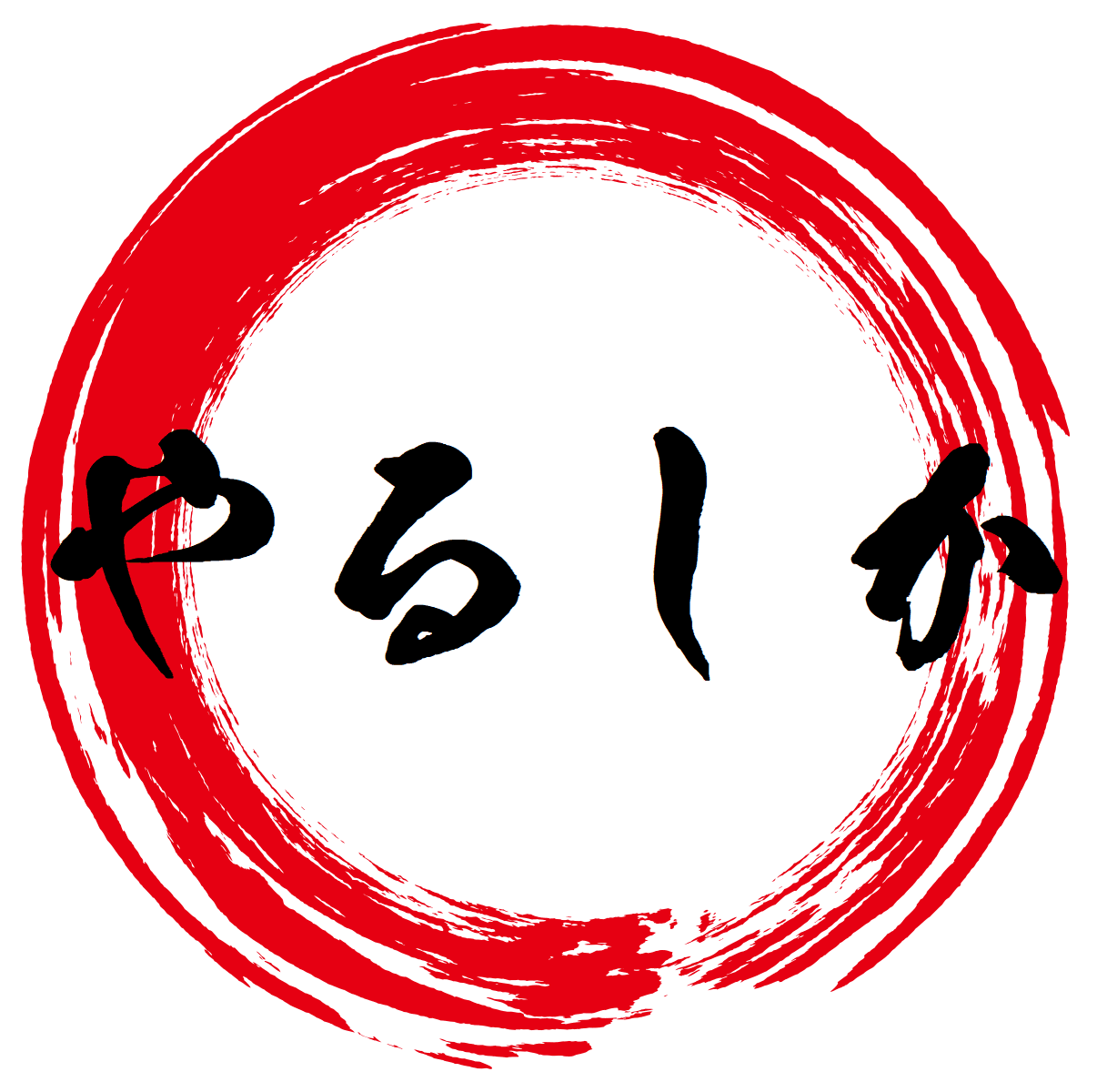消防設備士には実技というものがあります。
最初は本当に何もわからなさすぎて、
電気工事士みたいに何かを作ったり、手を動かしてやるものなのかな?と思っていました。
甲種と乙種は実技に大きな違いがあるので、それを踏まえてどちらを受けた方がいいかの観点でも書いています。
どちらか悩んでいたり、まずは乙種かなと考えている人がいれば参考にでもなれば幸いです。

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
消防設備士の筆記
まずそもそもなんですが、乙種というのは筆記に関しては勉強する範囲が変わるわけではありません。
ほんの一部変わることもあるみたいですが、基本的には甲種で勉強することと一緒です。
だからテキストも甲種と乙種で兼用なのです。
だけども出題される問題数は45問から30問になります。
甲種の縮小版みたいな感じです。
これって結構リスクのあることなんじゃないかなとは思っていて、
乙種の10問中4問正解するのと、同じ科目で甲種で15問中6問正解するのでは結構印象が変わってくるのではないかと思います。
乙種だからと言って内容が簡単になるわけではないですからね。
消防設備士の実技
消防設備士試験には実技(鑑別大問5個、製図大問2個)というものがあります。
実技とはいっても、電気工事士見たいに何かを作ったりということはありません。
事実上の筆記です。
ただマークシートではなく、記述式なんですね。
実技に関しては鑑別という絵や写真を見て答える問題があります。
大問が5個あり、その中に小問があります。
例えば、写真(2枚)を見て、それぞれの名称と用途を答えよ
的な問題があったら、大問1の中に小問4問(写真二枚のそれぞれの名称を答える小問と用途を答える小問)の計4問あるって感じですね。
この小問に関しては2問くらいの時もあれば、6問以上だったり差があります。
この小問は注意しておかないと、一つ勘違いしていたり間違えたりすると、
芋づる式に減点されてしまうこともあります。(経験あり)
例えば大問の1つとして、この器具の名称と、それぞれの寸法を求めよ(小問4)
的な問題があったら、名称を他の器具と覚え違いしていたら当然寸法も違い、全て間違えてしまうので注意が必要です。
こちらも乙種と甲種で難易度に差はありません。
乙種との大きな違いは製図があることですね。
製図も大問が2問あり、小問がさらに何問にも分かれております。
製図には配管や配線を図面の足りない部分に書き込んでいくというものがあるのですが、
線を引くのは完全にフリーハンドになります。
これ結構長い線引かされたり、図記号を書き込んだりするので、
中々きれいに書けないこともあるとは思いますが、よっぽどではない限り気にしなくていいです。
ぼくも試験本番は相当汚かったです(笑)
正しい場所につながっていればいいです。
甲種は乙種に加えて製図を勉強するかどうかだけなので、段階を経るために乙から甲へと考えている人がいれば、
受けることができるなら確実に甲種からやった方がいいです。
ただ甲種は受験資格があるので、誰でも受けられるわけではないのでそこは注意が必要です。
大まかには、電気工事士の資格がある人とかですかね。
実技試験の配点は完全にブラックボックス
ちなみに実技の配点は完全にブラックボックスになっており、誰にもわかりません。
一説で有力なのは、シンプルに鑑別と実技が半々というものだったり、
あえて合格せずに1問ずつ解いていって、鑑別6で製図4の割合だと主張する猛者もいますが、
どれだけ調べたところで憶測の域を出ません。
なので、その割合ですら試験によって違うのではないかなーと僕は考えています。
けど体感上はざっくりとした配点はそんなものです。
配点がどうあれ結果は結果なので、知っても仕方がないのかもしれませんが、
落ちるなら落ちるで次の段取りがあったりして早く知りたいので、
そこくらいは公表してくれてもいいんじゃないかなと思いますね。
採点する側も人間なので、ギリギリなら内容次第で情状酌量で点をくれるという噂もありますね。
だから、わからない問題があってもとにかく途中まで書いたり頑張る姿勢も大事なのかなと思います。
部分点をくれたりするかもしれないですしね。
あまり無責任なことは言えませんが、とにかく書き込んでみるのはやってみる価値はあるかもしれないです。
どちらかを選ぶのなら甲種がおすすめ
甲種を受けるための受験資格がないけど、乙1が欲しいとか
会社で乙種で十分だからそれだけ取っといてとかなら全然いいんですけど、
もし受験資格があって、甲1と乙1どちらを受けようか悩んでいる人がいたら
僕だったら電気工事士を先に取得してでも、迷わず甲種をすすめますね。
その方が転職や、何かの面接の機会などがあるときでも乙種の人と並べたときに多少有利になるでしょうから。
頑張りましょう!