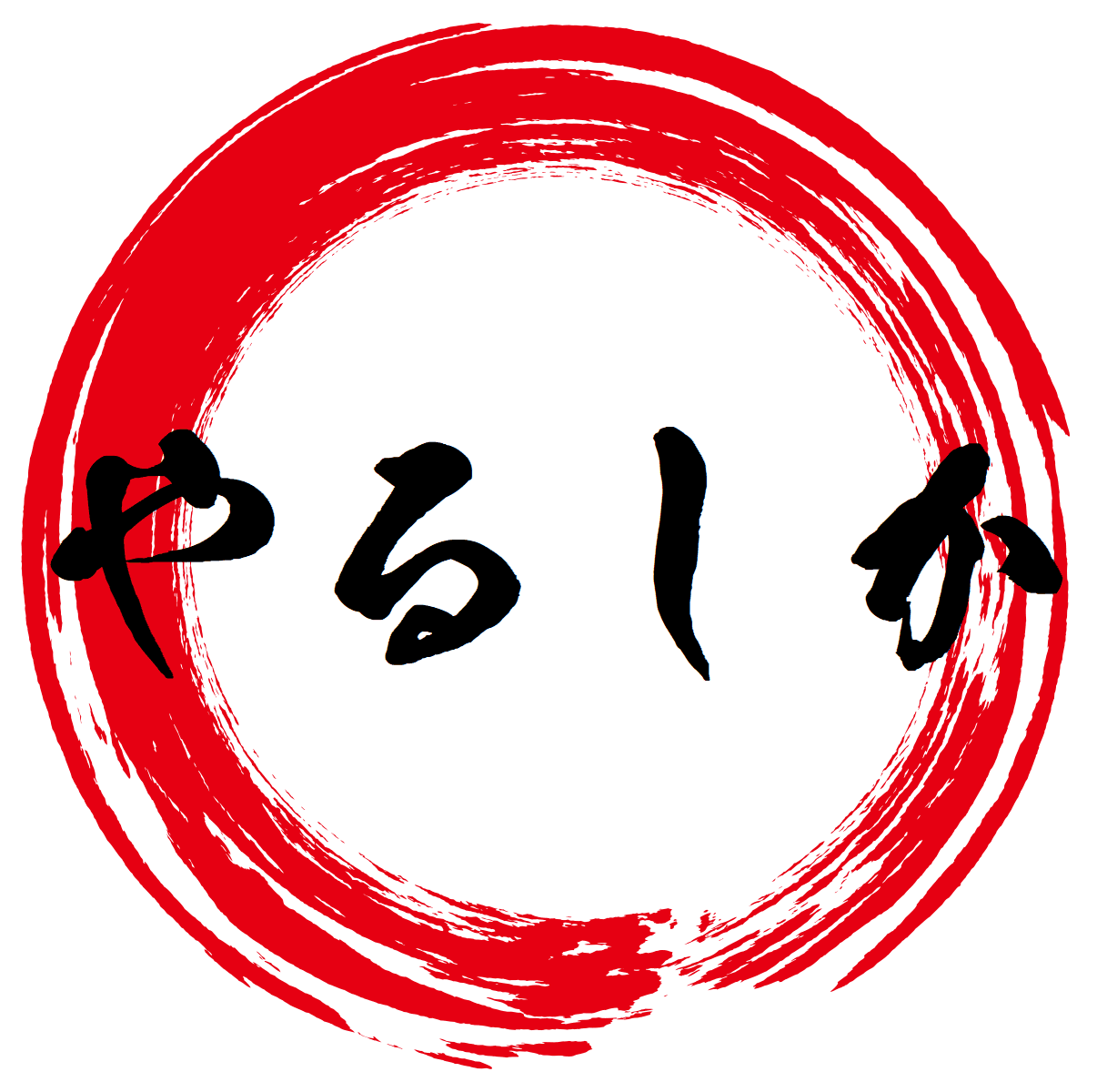消防設備士には足切り点(40%)が存在します。
手ごたえがそれなりにあったはず。
とか思っていても落ちてしまっている場合は足切りに引っかかっていることが考えられます。

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
足切り点(40%)とは
足切りラインは各科目カテゴリー40%で設定されており、
例えば基礎的知識で40%(40点)以上取らないと、法令や構造機能などがいくら100%(100点)でもダメなわけです。
免除なし(45問)の例を挙げると
| 科目カテゴリー | 問題数 | 正解 | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 法令 | 15問 | 15問 | 100% |
| 基礎的知識 | 10問 | 3問 | 30% |
| 構造機能 | 20問 | 20問 | 100% |
| 全体 | 45問 | 38問 | 84% |
全体の正解率(一番下)で見たらぱっと見申し分ないですよね。
でも基礎的知識が40%以下(赤字)なので、足切りでアウトです。
極端な例ではありますが、基礎的知識は苦手としている人も多いので、上記の表のようなことも考えられます。
合格基準は全体で60%
あと、各科目カテゴリーの正解率と全体の正解率は分けて考えられます。
全体の正解率では各カテゴリーの内訳は一切関係なく、全体からの割合で点数が出されます。
免除なし(45問)で受けた場合
| 科目カテゴリー | 問題数 | 正解 | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 法令 | 15問 | 6問 | 40% |
| 基礎的知識 | 10問 | 10問 | 100% |
| 構造機能 | 20問 | 10問 | 50% |
| 全体 | 45問 | 26問 | 57% |
足切りはOKですし、ぱっと見でも各科目の平均60%以上((40+100+50)/3=約63%)で合格してそうなんですけど
各科目のパーセントを合わせた平均ではないんです。
合格の60%には45問から27問正解する必要があります。
この例の場合、全体の正解数が、26問なので、
26問は45問中だと57%なので惜しくもアウトなわけです。
なので、全体の正解率も意識はしておかないとダメなんですね。
免除科目があると配点が変わってくる
これらは免除なしの例なので、免除ありの場合は当然配点の割合も変わってきます。
免除された科目が正解扱いになるわけではありません。
法令の例を挙げると
| 問題数 | 正解 | 正解率 | |
|---|---|---|---|
| 法令免除なし | 15問 | 6問 | 40%(セーフ) |
| 15問 | 5問 | 33%(アウト) | |
| 法令免除あり | 7問 | 3問 | 42%(セーフ) |
| 7問 | 2問 | 28%(アウト) |
免除しないと15問中6問正解までセーフ、正解が5問以下で足切りでアウトだったのが、
免除した場合7問中3問までセーフ、正解が2問以下で足切りでアウトになります。
要は一問当たりの配点がかなり高くなります。
免除などによって変動するので表は参考程度にとどめておいてください。
免除の配点や足切りまとめ
需要があるかはわからないですが、まとめてみました。
免除するかどうかも込みで、戦略の参考に使ってみてください。
足切りというルール
足切りというルールは消防設備士にかかわらず科目のある資格試験に存在します。
僕の取ったものでいうと
危険物取扱者
ボイラー技士
ですかね。
知識が偏りすぎてもダメなので、最低限のルールですね。
危険物取扱者では同じ消防試験研究センターからの試験なのですが、
合格基準は60%、足切りは60%と高めです。
要は足切り=合格基準点ですね。
なので試験によって、それぞれの基準で足切り点は設定されています。
ボイラー技士は消防設備士と同じく各科目40%、全体で60%です。
足切りについては少し意識しておいた方がいいと思います。