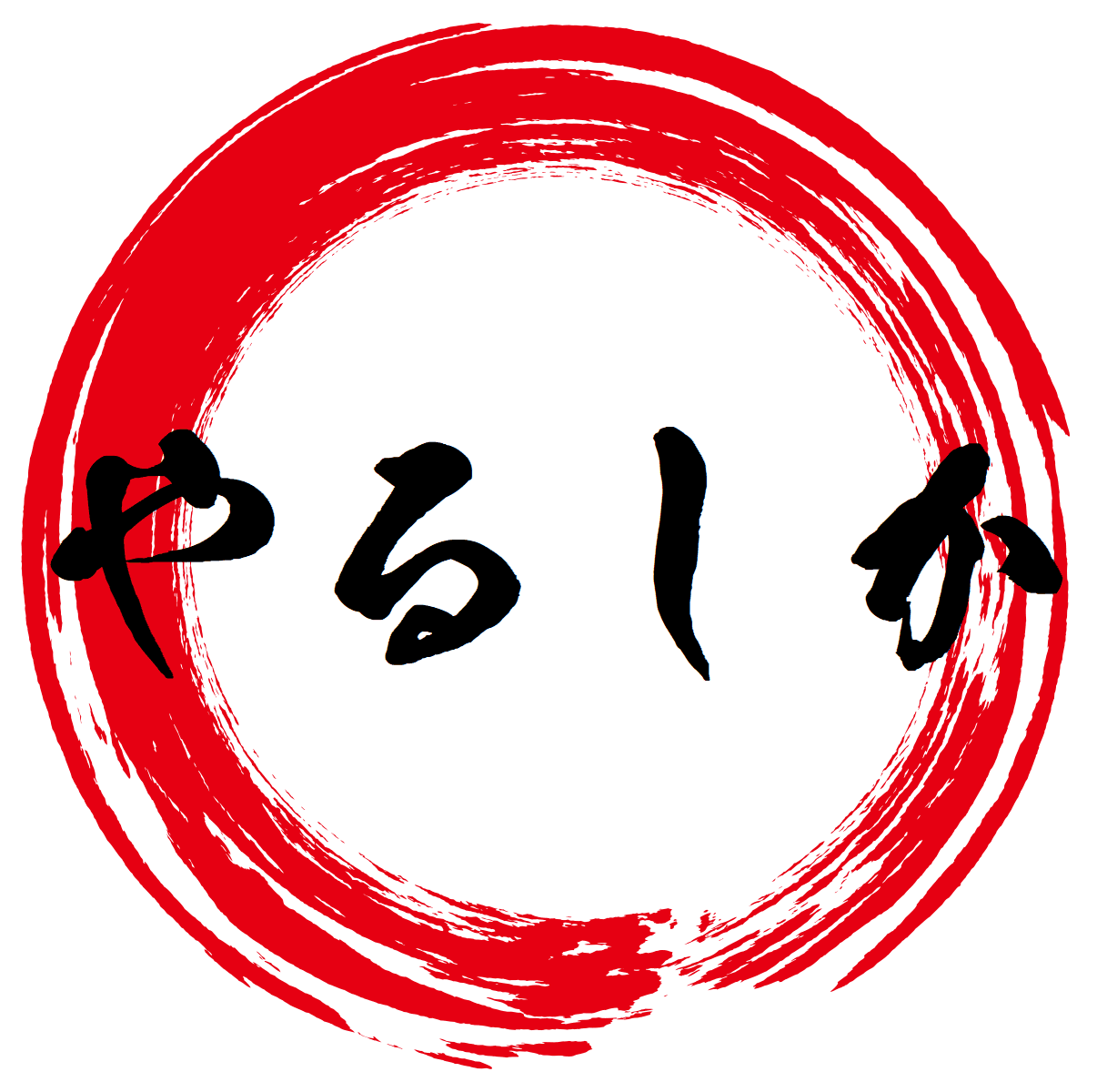消防設備士 甲種2類について、試験概要をまとめてみました。
自分ならここが気になるかなという項目を詰め込んだので、こういうのでいいんだよ感はあると思います。
あくまで概要なので、詳しい日程は消防試験研究センターのHPで確認してください。
合格率
| 甲2 | |
|---|---|
| 平均 | 33.5% |
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024(R6) | 3,890 | 1,061 | 27.3 |
| 2023(R5) | 3,865 | 1,170 | 30.3 |
| 2022(R4) | 3,636 | 1,034 | 28.4 |
| 2021(R3) | 3,791 | 1,370 | 36.1 |
| 2020(R2) | 2,895 | 960 | 33.2 |
| 2019(R1) | 3,023 | 1,095 | 36.2 |
| 2018(H30) | 3,127 | 1,113 | 35.6 |
| 2017(H29) | 3,156 | 1,224 | 38.8 |
| 2016(H28) | 3,313 | 1,086 | 32.8 |
| 2015(H27) | 3,025 | 892 | 29.5 |
| 2014(H26) | 2,783 | 1,028 | 36.9 |
| 2013(H25) | 2,540 | 952 | 37.5 |
| 2012(H24) | 2,713 | 942 | 34.7 |
| 2011(H23) | 2,812 | 968 | 34.4 |
| 2010(H22) | 2,803 | 975 | 34.8 |
| 加重平均 | 47,372 | 15,870 | 33.5 |
| 単純平均 | 33.8 |
※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。
難易度
平均で34.3%程なので、見た目の合格率よりははるかに難しいと思います。
甲種2類は甲種1類を合格したり受験した人が受ける場合が多いと思うので、見た目の合格率より難しいと思います。
故に消防設備士では一番難しいと思っている人は多いです。
合格率は簡単な時で38.8%
難しい時で28..9%ですね。
厳密には年に何回もあり、全国的に行われている試験ですので、試験運が関係してきますが、
簡単な回に当たる可能性もあります。
簡単とはいえ合格率38%程は想定しておいた方がいいです。
受験資格
甲種は誰でも受けられるわけではありません。
受験資格は結構あるのですが、このブログですすめているものとしては
電気工事士の資格を持っている人。
ですね。
第三級陸上特殊無線技士という資格は近年の合格率は85~90%台で安定しているのでいいみたいです。
ただし第三級陸上特殊無線技士は科目免除はないので免除派の僕としては特におすすめはしていません。
その他受験資格は消防試験研究センターのHPを確認してください。
免除
免除に関しては少しややこしくなるので、こちらをご覧ください。

受験料
| 申込方法 | 受験料 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 6,600円 | クレジットカード決済 コンビニ決済(+手数料) ペイジー決済(手数料原則無料) |
| 書面申請 | 6,600円 | 払込取扱票(+手数料) |
試験申し込み期間
上記にもありますが地域差があるので消防試験研究センターのHPでご自身の地域をご確認ください。
| 締め切り日 | 地域差があるが試験日の1~2か月前くらい |
|---|---|
| 試験申し込み期間(期限) | 地域差があるが申し込み開始後1~2週間くらい |
申し込み方法(願書)
消防設備士の甲種は受験資格が必要になるため、ほぼほぼ書面での申請がメインになると思います。
免除をする際にも証明書が必要となりますので、その際も書面での申請が必要になります。
電子申請が可能なのは,免除をしない方で、過去に甲種の資格を取得して免状が手元にある方になっております。
書面での願書が必要となる場合は最寄りの消防署や一部書店など最寄りの配布場所まで行きましょう。
いくつかの情報ではわかりにくい表記もあるんですが、願書のダウンロードはできません。
願書は受付日の約1カ月前より配布とありますが、毎年願書の中身は一緒なので、去年までのも使えます。
場所にもよるかもしれないが僕の最寄りの消防署の出張所にはなく、大きめの消防署に行ってほしいとのことでした。
当然ですが何通もらっても無料です。
直接の願書提出
受けようと思う県の消防試験センターに直接願書を持って行っても大丈夫です。
その際は現金で直接受験料を払うことはできません。
郵便局で払込取扱票で振り込んで支払った証明書を貼るといったことは同じです。
送る用の簡易書留代が浮くくらいですね。
そして他の県での消防設備試験の受験も考えていたため、
他県とは言え同じ消防試験研究センターなのでいけるかなーと淡い期待を抱いて聞いたのですが、
「は?」みたいなリアクションをされたので、すかさず「ですよねー」的な感じでごまかしました。
管轄というか、それぞれの県はまったく別みたいです。
試験日
| 消防設備士 甲種2類 | |
|---|---|
| 消防試験研究センターのHPを確認 | 各都道府県で年数回実施 |
都道府県によって試験の日程はバラバラなので上記のリンクから要確認してください。
どの県も数回は試験実施は行われています。
毎年の試験日程の発表は毎年2月末頃になっています。
受験地
どの都道府県でも開催されています。
消防試験研究センターのHPを参照してください。
試験時間
| 免除なし | 法令免除 | 基礎的知識&基礎的知識免除 | |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 3時間15分 | 3時間 | 2時間30分 |
| 退出可能時間 | 35分 | ||
| 着席時刻 | 試験開始時刻 | 入室禁止時刻 |
|---|---|---|
| 30分前 | 地域によって異なります | 試験開始時刻から30分 |
一応着席時刻を遅れても受けれますし、30分の遅刻まではいいらしいのですが、
きちんと時間は守りましょうね。
問題数
45問
免除によって変わってくるので、詳しくは免除の項目をどうぞ
科目
| 科目 | 問題数 |
|---|---|
| 消防関係法令 | 15問 |
| 基礎的知識 | 10問 |
| 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 | 20問 |
| 実技(鑑別大問5問・製図大問2問) | 7問 |
出題形式
| 出題形式 | |
|---|---|
| 1~4からの四肢択一 | マークシート方式 |
合格基準
60%以上正解で合格です。
足切り点が各科目40%以上必要なので、まんべんなく知識が必要となります。
受験票
書面申請は郵便はがきとして一週間前までに届きます。
電子申請の場合も一週間前までには受験票はメールで来ます。
自分の場合は
危険物取扱者試験の場合は13日前に届きました。
消防設備士試験の場合は10日前に届きました。
(危険物取扱者試験と消防設備士試験はどちらも消防試験研究センターの運営)
ダウンロードしたものを印刷してから指定された写真を貼ります。
持ち込み
受験票(縦4.5cm×横3.5cmの写真をのり付けしたもの) ※複数受験者は類ごとに合計2〜3通必要
鉛筆又はシャープペンシル(いずれもHB又はB)
プラスチック消しゴム
上ばき(受験票に記載してある場合)
時計は余計な機能が付いていないものは可です。(僕はチープカシオの一番シンプルなものでした)
ただし、あまりないとは思うのですが、会場によっては掛け時計があるというので、外されましたね。
製図があるのですが、定規は不可です。フリーハンドで書かされます。定規くらいは可にして欲しかったですね。
たまに複雑な計算(僕にとっては)がある場合があるのですが、電卓も不可です。
試験後の問題用紙持ち出し
不可
試験問題・解答の公表
問題と解答の公表はありません。
正答率(%)はハガキで通知されます。
合格発表
| 消防設備士 甲種2類 | ||
|---|---|---|
| 合格発表 | 消防試験研究センターのHPを確認 | 試験実施日から10日~38日程 |
合格発表は東京は早い傾向ですが、短くても10日はあります。
東京でも17日間や26日間かかるときもあります。
調べた範囲では最長で38日かかる県も複数ありましたが、その県でも別の日程では16日間や17日間で発表だったり、
バラバラですね。
免状が届くまで
各都道府県で、はがきに書かれている免状交付締切日までに出すと、
書かれている免状交付日を目安に発送されます。
基本的に発行されたらすぐ発送されるので書かれている日付より早い場合もあります。
経験上は早いことはあっても、遅いことはなかったです。
日付の指定はできません。
複数受験(同時受験)
地域にもよりますが、最初の乙種と甲種は時間帯がずれていた場合、同日に受けることができます。
僕は甲種1類と乙種6類、甲種5類と乙種7類を同時に受けたことがあります。
最後に
ここだけ見ておけばいいというくらいにまとめました。
ここまでで、消防設備士甲2の全体像や準備に必要なものは整理できたと思います。
甲2の勉強方法やテキストなどについては以下のリンクからどうぞ。