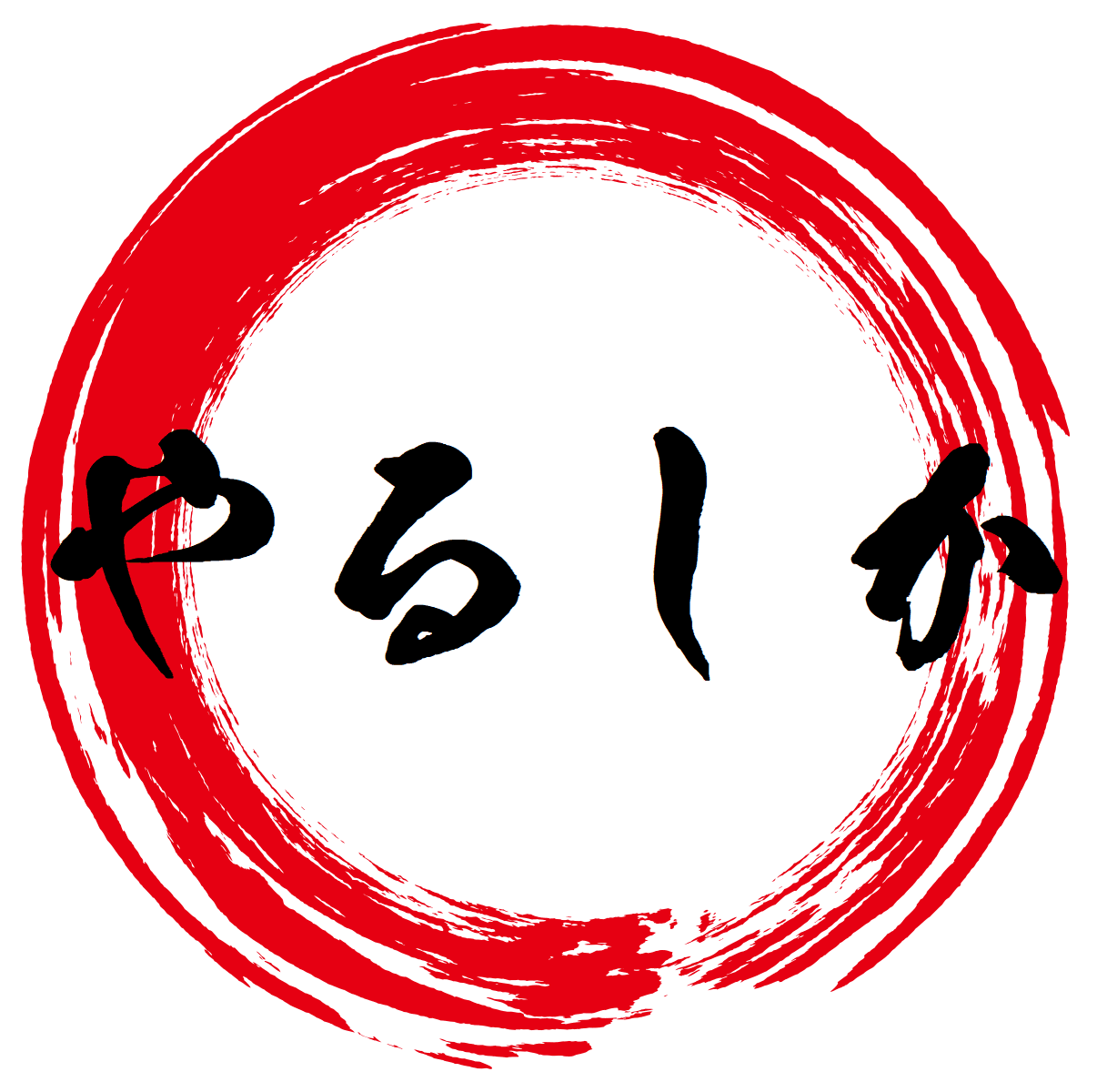自分にあった記憶術を模索していく中で開発した技があります。
それが今回師紹介する
「数字召喚法」と共に記憶の2大柱として使用してきたうちの一つである
落書き具現法
です。
「イラスト法」はなんかイラスト界隈で埋もれそうだし、
「絵法」は短いし、いいかと思ったんですが、
恵方が強すぎて表に出てこれるイメージがわかないです(笑)
なので落書き具現法にしました。
僕はこの方法をこの資格だけでなく、勉強法として広く知って欲しいんですね。
落書き(絵)がみんなを助けてくれると思っています。
もう一つ数字イメージ変換法というのをヒントにした
数字召喚法っていうのもあります。

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら
- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得
- 一応ビル管と電験三種はあります
- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます
- 役に立つライフハックを伝授
- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です
落書き具現法とは
教科書に書いた落書き
これがヒントになっております。
教科書に描いた絵ってなぜか印象や記憶に残っているあるあるを
前面的に手法として押し出した記憶術になります。
カナダのウォータールー大学での研究でも
絵を描くことでの記憶力は向上するという結果が出ているので、
その信頼性は折り紙付きです。
そもそもこの僕ですら効果を実感したので、間違いないです(笑)
落書きにも種類がある
graffiti・・・壁に書かれた落書き
sketch・・・ノートや手帳に書かれた”本格的な”落書き
doodle・・・ノートや手帳に書かれたいたずら書き
scribble・・・”殴り書き”のような落書き
一応勉強を意識して書くので、いたずらともニュアンスが違うのですが、
本格的でもない気がするので、
この中で強いて言うなら
doodle ですかね。
絵自体は適当でもいいので、
scribble
でも効果は十分にあります。
そのうち英語のニュアンスがわかってきて,
sketch
だったかーwww
って思う可能性めっちゃあります(笑)
きっかけ
そもそものきっかけは
乙4の時に公論本で感じた文字だけのとっつきにくさを
後に太陽本で字だけの理解からイメージで補った時に、よりスッと頭に入ってきたんですよ。
その時に、あー絵やイメージでしっかり理解するって大事なんだなーと思ったのがきっかけでした。
記憶術ではイメージが大事なんて当たり前すぎる世界なので、何を今更と思われるかもしれないんですけど、
身をもって体感した感じですね。
スキーマ
スキーマという概念があり、
物事は自分の理解できないものは判断しにくい、できないようにできています。
そこで字だけの情報から、絵や写真を見たときに途端に記憶に入ってくるのです。
体感することで違いを感じる
で、乙3、5,6の時に落書き具現法のプロトタイプというか
覚えるものが多すぎて頭に入ってこないので、
問題文に書いてあるそれぞれの危険物の特徴を落書きで描いていったんですよ。
一級ボイラーもしなきゃならなくて、最後の2週間くらいは正直危険物の乙種は放置していました。
2週間も、違う試験のことを集中してやると、当然記憶からかなりうすれていて
乙3、5,6は一級ボイラーの4日後の試験なので、これはまずいなーと思っていました。
乙種の勉強を再開して、
そのノートを見ながら復習した時に、記憶から消えていたはずのことが、
ズルズルっと引き出されてきたんですよね。
不思議な感覚でした。
これならいけるかもしれない。
結果、3類は9割 5類は10割 6類は9割
で無事合格することができました。
前日は深夜まで仕事、当日も午後から仕事で早く終わらせる必要があったので、
決して万全とはいえない状況でした。
用意するもの
チラシやプリントの裏でもできるので、結構自由度は高いです。
僕は最終的にエクセルで枠を区切って漫画のコマみたいにし、
それを両面印刷して、ノートとして使っていました。
けどなんかめんどくさくて、その辺の手に取れるプリント裏を使ってたことも全然あります。
しかも使ったものもA4やB5とバラバラですので、
ガチガチにこうしなきゃとか考えなくていいです。
気軽に気楽にやりましょう。
やり方
まぁなんてことはないのですが、
まず問題を解いてみて、やっていてわからない部分を
絵をメインにしてノートに描いていく。
って感じですかね。
イメージは頭の中で覚えますが、
それを絵で描いて具体的に見える化するので、記憶がより強固なものになります。
結構無理があるような変換も、
絵に起こして記録していけば覚える事ができます。
数字や数値を記憶することも多いと思うので、
数字召喚法で変換したものを、問題文と結び付けて絵に描いていきます。
便利なのはグーグルなどのイメージ検索ですね。
数字召喚しにくいような、自分のボキャブラリーの中にないような文字の羅列も
ググったら見つかることもあります。
絵は汚くても大丈夫
絵はうまくなくちゃいけないのって思うかもしれませんが、
全然うまくなくても大丈夫です。
僕はめちゃくちゃ下手ではないのでしょうが、上手いとも言われたこともありません。
よくある、身体全然描けないとか、その程度の画力です。
適当にささっと描いた絵でもしっかり記憶には残るのです。
イメージが見つからなくても大丈夫
それでも絵が見つからない場合があります。
こういった設備関連の資格を受けていると、写真がある時はまだいいのですが(それでもわかりにくいものは多い)
そのものの写真がある時などごくわずかなんですよね
なので私のやり方は、無理やりそのものを自分の中で作り上げて、イメージしてしまうといったやり方です。
特に設備とかの試験では、ググってもそのものが出てこないなんてことはザラにあります。
その場合は、自分で作ってしまいましょう。
例えば第一種冷凍機械責任者で出てきた、
「遠心圧縮機」なんか調べても、描きづらいし、わけわかんないんですよ。
イメージはあってもイメージしづらいし、そもそも画像がない事もある
なので僕の中の遠心圧縮機はこれでした。
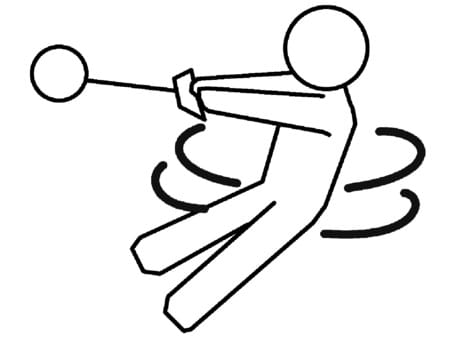
は?なにそれ?と声が聞こえてきますね。
いいんです。
僕が遠心圧縮機はこれだと決めたら、これが遠心圧縮機なんです。
それでいいんです。
無理矢理何でも当てはめていくので、
第一種冷凍機械責任者で使う数学の公式を覚えるのにも
もちろんこの記憶術を使いました。
勉強と関連性のない絵でも大丈夫
別にやっている勉強と関連のないものが登場しても全く構わないです。
なので、ノートの中身はその人の知っていることや調べた物などで左右されるので、
十人十色となり、人が見てもよくわからないものとなる事が多いです。
なので共有は正直難しいと思いますが、(したことないので、できなくはないかなとも思っていますが)
自分はしっかり分かっているので何も問題はないわけです。
過度な期待は禁物
僕がここでゴリ押ししているからといって、
一度描いたものですぐに覚えられるような魔法なような効果は期待しないで下さい。
あくまで記憶術のひとつであり、記憶を補助するためのツールです。
他の記憶術もそうであるように、結局は繰り返し覚えるという作業は必要ですね。
この記憶術は、描いている時よりも、
描いた後に問題集と並行して繰り返し覚えるときに
最大限の効果を発揮すると思っております。
記憶の補助として、記憶力をブーストしてくれるイメージですかね。
場所法(記憶の宮殿)のような役割もある
僕は、場所法はあまり資格では使えないかなーと思っているのですが、
この記憶術は
あ、あのコマのここに描いていたかなー
とある意味場所法のような役割を果たす時があります。
なので、場所法の役割もありつつ、資格試験との相性はいいと思います。
それを見ても覚えられなかったら、
もっといい覚え方はないか模索するか、
そこを蛍光ペンなどで、チェックしておいて、
重点的にやるなどをします。
描いた絵がかわいくなってくる
この記憶術で勉強を進めていくうちに
この描いた絵たちが味方になったような感覚になります。
絵たちが自分を助けてくれるのです。
なので、
こんなこと書くと、気持ちわるがられると思いますが、
自分の描いた絵たちがかわいく、愛おしくなってきます。
ありがとうなって本当に言っていました(笑)
もし仮に落ちても、そのノートは再受験の際に絶対に役に立つと思います。
楽しいっちゃ楽しいけど、しんどいっちゃしんどい
僕は以前に、
勉強は楽しくなることは結局なかったって書いたんですけど、
そんな中でもこの記憶術は楽しい部類には入ったんだと思います。
けれども、どんなしょうもない絵を描いている時でも必死でしたし。
あまり絵を描いてても楽しかったなーって記憶がないんです(笑)
気持ちに余裕が持てれば、楽しい勉強法になるのかもしれないなと思いましたね。
なので、僕は今後学習していくことでも絵は絶対に取り入れます。
全然勉強時間がない場合
これはしょうがないので、
せめて文字にして想起しやすいようにする。
絵に描いてしまうのと大差ないかもですが、やらないよりはましだと思います。
けど、簡単な絵だけでも記憶に残るので、なんだかんだ絵にした方がいいと思います。
一夜漬けなどの場合も、頭の中で想像してイメージにしておく。
これをするとただ数字の羅列や想像がつかないものを文字で覚えるよりも思い返しやすいと思います。
結局のところ、簡単でもいいから絵にしてしまいましょうってことですね。
いまだに試験当日に適当に描いた絵が頭に残ってたりします。
それほど強烈なんですね。